問題28
労働者災害補償保険(労災保険)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
(ア)
労災保険は、労働者の業務災害や通勤災害による傷病等を事業主に代わって補償することを目的としており、労働者を雇用する事業主等には適用されないが、中小企業の事業主、一人親方などについては、一定の要件のもと、労働者に準じて労災保険に特別加入することができる。
(イ)
労災保険では、労働者が業務災害による傷病のために休業し、賃金の支払いを受けられない場合、その被災労働者に対して療養補償給付に代えて休業補償給付が支給される。
(ウ)
労災保険からの保険給付は、療養補償給付、休業補償給付、傷病補償年金、障害補償給付、介護補償給付および遺族補償給付のいずれも非課税扱いとなる。
問題29
労働者災害補償保険(労災保険)に関する次の記述のうち、誤っているものを選びなさい。
(ア)
労災保険では、業務災害による休業補償給付を受給していた労働者が、療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治らず、かつ、傷病等級第1級~第3級に該当する状態が継続する場合、その被災労働者に対して休業補償給付に加えて傷病補償年金が重ねて支給される。
(イ)
労災保険では、業務災害等が第三者の行為によって生じた場合で、その災害に対して保険給付が行われたときは、その給付の価額の限度において、国(政府)は、被災労働者またはその遺族が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する。
(ウ)
労災保険では、休業補償給付、傷病補償年金、障害補償給付、遺族補償給付については、それぞれの保険給付に加えて特別支給金が支給される。
問題30
労働者災害補償保険(労災保険)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
(ア)
労災保険の適用労働者は、事業所に勤務する常用労働者に限られ、臨時雇、日雇、アルバイト、パートタイマーは該当しない。
(イ)
労災保険の保険料は、事業主が労働者に対して支払った賃金総額に業種別に区分された労災保険率を乗じて算出され、事業主が全額負担するため、労働者の負担はない。
(ウ)
労災保険において、労働者が業務災害による傷病のため休業し、そのために賃金を受けない場合、その被災労働者に対し、休業した4日目から1日につき給付基礎日額の60%に相当する額が休業補償給付として支給される。
問題31
労働者災害補償保険(労災保険)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
(ア)
労災保険では、業務災害による休業補償給付を受給していた労働者が、療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治らない状態が継続している場合、その傷病等級にかかわらず、被災労働者に対して休業補償給付に加えて傷病補償年金が支給される。
(イ)
労災保険では、労働者の業務災害による傷病が治癒したときに、被災労働者の身体に一定の障害が残った場合には、その被災労働者に対して障害補償給付が支給される。
(ウ)
労災保険では、障害補償年金または傷病補償年金の受給者のうち、障害等級または傷病等級が第1級の者と第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している者が、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、現に介護を受けている場合には、月単位に所定の額を限度として、その介護費用(実費)に対して介護補償給付が支給される。
問題32
雇用保険に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
(ア)
雇用保険を管掌するのは、国(政府)である。
(イ)
雇用保険における就職促進給付とは、失業した被保険者の再就職を援助・促進することを目的とする給付である。
(ウ)
雇用保険における失業等給付は、目的、種類により、求職者給付と雇用継続給付の2種類に大別される。
問題33
雇用保険に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
(ア)
雇用保険では、一般被保険者が解雇により失業した場合で、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あるときは、原則として4週間に1回、失業の認定を受けた日について、賃金日額の全額が求職者給付の基本手当として支給される。
(イ)
雇用保険における失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付および雇用継続給付の4種類に大別され、いずれも非課税扱いとなる。
(ウ)
雇用保険の雇用継続給付における介護休業給付とは、介護休業を取得した者の失業を予防するために支給される給付のことをいう。
問題34
雇用保険に関する次の記述のうち誤っているものを1つ選びなさい。
(ア)
雇用保険の育児休業給付では、育児休業期間中の賃金が休業開始時と比べ80%未満に低下することが支給要件の1つになっている。
(イ)
雇用保険では、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、同一の事業主の適用事業に31日以上引き続き雇用されることが見込まれるパートタイム労働者(短時間就労者)で、労働条件が明確に定められている場合は、一般被保険者となる。
(ウ)
雇用保険の保険料は、失業等給付および育児休業給付に係る部分についてはその全額を事業主が、また雇用保険二事業に係る部分については事業主と被保険者が折半で、それぞれ負担している。
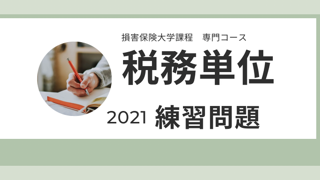

コメント